レポート
現代版寺子屋 スクール・ナーランダwith JT‐ONLINE
日 時: 2020年10月25日(日) 13:00~17:20 Youtubeにてライブ配信
会 場: 築地本願寺 講堂(東京都中央区築地3-15-1)
テーマ: 冷たいお金の集中から温かいお金の廻りへ
現代社会は、お金による格差と分断が深刻化しています。しかし、本来「経済」は「経世済民=世を経(おさ)め、民を済う」ためのものであります。浄土真宗の門徒が多かった近江商人は、「三方よし(売り手よし、買い手よし、世間よし)」という仏教の教えに由来する商売の理念を大切にしてきました。そして、今またこうした姿勢がポスト資本主義の一つの形「公益資本主義」として注目を集めており、このような浄土真宗の教えに基づく考え方を通して、温かいお金が巡る社会について考えました。
講 師: 西部忠先生 (進化経済学者 )
廣渡清栄先生 (日本たばこ産業株式会社 副社長)
成田 智信先生 (浄土真宗本願寺派僧侶)
― 講義レポート ―
■「恩返しではなく、恩送り」 西部忠先生
|
進化経済学者の西部先生からは貨幣の過去・現在・未来について、「お金」にまつわる起源、歴史的な過去を振り返りながら、現在について話しをしつつ未来を展望する、というお話しをいただきました。 講義中、先生は『互酬(ごしゅう)』という大変興味深い言葉を紹介されました。英語で説明すると『ペイバック(PeyBack)』とは、贈与と返礼。それに対して、『ペイフォワード(PeyForward)』は、贈与の回し合い、「互酬」。 『あたたかいお金の廻り方』も、この考え方が社会で持続可能にしていくあたたかいお金の廻り方ではないかとお話いただきました。 |
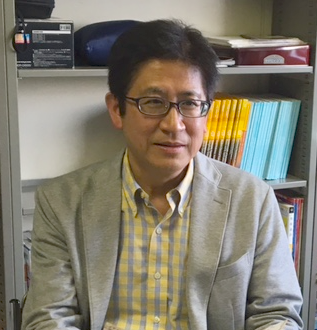 |
■「人の時を想う」 廣渡清栄先生
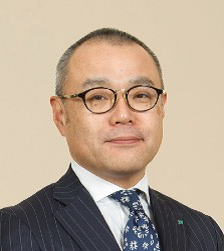 |
『会社は社会の公器である』。廣渡先生は、パナソニック創始者松下幸之助の言葉を引用され、「会社とは何のために存在するのか?」についてお話しされました。 また、廣渡先生は『モノの豊かさと心の豊かさ』について次のようにお話されました。今の世の中はテクノロジーの親展に伴って、社会全体が合理的になって進化している。その一方で、人の個性の多様性、曖昧さ、"それもまた人間らしいじゃないか"と受け入れる社会がある。そういった「人間らしさ」の対極に今の「テクノロジー社会」があるのではないか。「人間らしさ」=「心の豊かさ」。それに対して「テクノロジー社会」=「息苦しさ」。この「息苦しさ」は、社会が便利に進化すればするほど、今後益々高まっていくのではないか。そのような中で我々はテクノロジ̶の進化によって忘れ去られつつある「人の心の豊かさ」に寄り添って生きていく。社会の中で色んな個性があってもいいではないか。 我々JTは、「人間らしさ」、「心の豊かさ」の領域を世の中に問い続けていく事によって、"あがき続ける"。そんな存在でありたい。「心の豊かさ」を独自の付加価値として、人間らしさの領域で、あたたかいお金の循環をつくる、そんな存在でありたい。 まさに、JTの企業広告に出てくる言葉、『人の時を想うJT』その理念の背景を聞かせていただいたようなお話しでした。 |
■「お金×仏教~出会うことの大切さ」 成田智信先生
|
かつて浄土真宗門徒が多かった近江商人の仏 教の教えに由来する経営哲学、「三方よし(売り手よし、買い手よし、世間よし)」についてお話し下さいました。 近江商人は、江戸時代から明治にかけて活躍した商人で、近江国(現在の滋賀県)に本宅を置 き、他国へ行商して歩いた商人の総称です。大坂商人、伊勢商人と並ぶ日本三大商人のひとつと いわれています。 彼らの経営哲学のひとつとして、仏教の教えに由来する『三方よし』を、商売に対する姿勢・理念として大切にしてきました。自らの利益のみを求めることなく、多くの人に喜ばれる品を提供 し続け、さらに利益が貯まると無償で橋や学校を建てたり、社会に対して積極的に貢献したのです。つまり『三方よし』とは、『商売において売り手と買い手が満足するのは当然で、社会に貢献で きてこそ良い商売といえる』という、現代の経営哲学に通じる考え方を持っていたのです。 近江商人の理念は単なるスローガンではなく、仏さまの教えそのものでした。そこには具体的な 人と人との営みがあったと、成田先生。「売り手良し、買い手良し、世間良し」は、別の捉え方として、「自分良し、相手良し、世間よ し」という捉え方もある。「自分良し、相手良し、世間よし」というのは、利益を上げることだけが目標になっていません。 利益は事業継続のための必要条件です。「目標」ではありません。そこにある「理念」がとって も大事。 仏教を生きる事は「理念そのものを生きる」こと。理念が仕事になる。そんな現象が 近江商人でしたとお話いただきました。 |
 |
【 Y 】
