レポート
「セクシュアリティと信仰」平良愛香さん|第3期 思春期・若者支援コーディネーター養成研修会
「思春期・若者支援コーディネーター養成研修会」は僧侶・寺族を対象として、思春期・若者の生きづらさについて理解を深める研修です。
今回の講師の平良愛香(たいらあいか)さんは1968年沖縄生まれ。この年はベトナム戦争の真っ最中。当時、沖縄はアメリカの一部であり、ベトナム戦争に巻き込まれていました。第二次世界大戦中は爆弾を落とされる側でしたが、この時は爆弾を落とす側になっていました。これは沖縄という地が、被害者であると同時に、加害者であるということになっていると話す平良さん。そんな想いが交錯する沖縄で生まれた平良さんのお名前「愛香(あいか)」は、聖書の中にある平和を泣き叫び求める「哀歌(あいか)」に由来しているそうです。(講義実施日:2020年11月4日)
本記事ではスタッフの藤井 (ふじい) が、受講して印象深かった気づきや学びをレポートします。
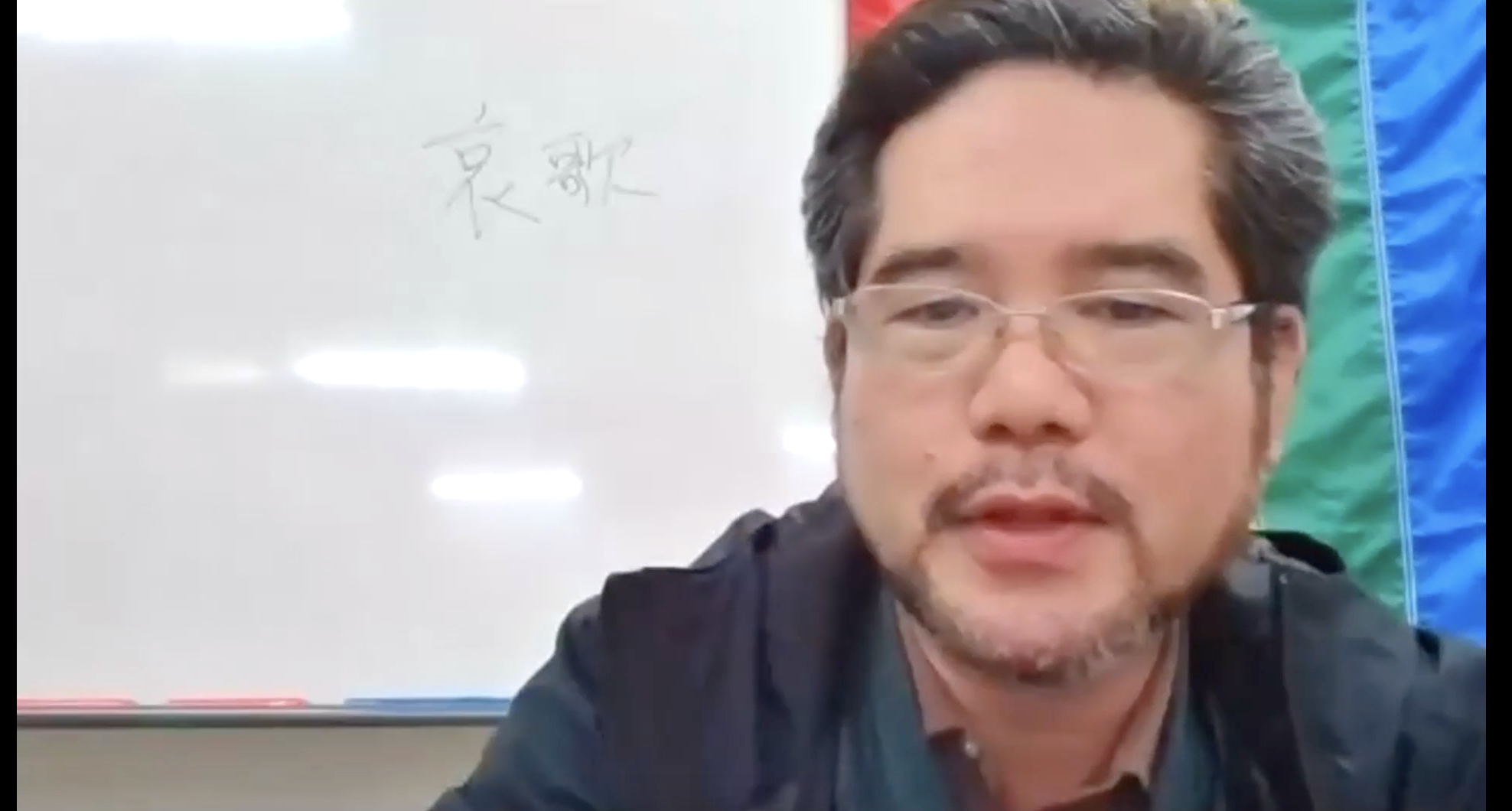
(講義の様子)
トランスジェンダーの人が抱える名前の壁。「愛香」のジェンダー
子どもの頃は、女の子と間違われることが多かった名前が嫌いだったという平良さん。ある時、お母さんに「この名前、好きじゃない」と言うと「変えればいい」と返事が返ってきて拍子抜けしたそうです。「親がつけた名前なのに、なんてことを言うの!」とか「沖縄の祈りを込めてつけたのに悲しい」とか言われると思っていたので、驚きました。この時から「愛香」という名前の受け止め方に少しづつ変化が生まれたのです。
"名前をどうするかを悩みに悩んで、最終的に選んだ名前は今までと同じ「愛香」でした。それまでは「愛香」という名前は親から押し付けられたもので、苦痛だったんです。けど、一度手放して、さらに自分で再び掴み取った名前は、もはや押し付けられたものではなかったんですね。窮屈じゃなかった。これでやっと心置きなく生きていけると思いました。
だから、自分の名前が嫌でしょうがない人がいたら「変えればー!」と思っています。他の人に押し付けられたもので生きるのはもったいないと思います。"
牧師として男性同性愛をオープンにして活動される平良さんの元には、本名/戸籍名でない名前で、教会に来られる人もたくさんいらっしゃいます。トランスジェンダーの方にはそういった方が多いのです。
"トランスジェンダーの人はみんな性別を変えて生きている人が多いと思われているけど、いろんな状況でそれができない人がいます。けど、本当は、心の中では女性として生きていきたいと思っている。
だから、教会では「あなたの納得いく名前を使えばいい」みんながそれに合わせると言えるんです。キリスト教でもいろんな考え方がありますが、どんな人も自分らしく生きていったらいいですよね。
名前だけじゃないですよ。生き方が本当に自分で選んだものなのか、親に押し付けられてはいないか。期待されているからと、社会に押し付けられた生き方を選んではいないか。女性だから、長男だからとか⋯⋯。本気でそれが嫌だと思ったら、違う生き方を見つけようとすればいい。それを周りも応援すればいいと思っています。"
性の3つの単語の意味
①Sex:性、生物学的な性。オス、メスについて
②Gender:ジェンダー(社会的性・文化的性)
③Sexuality(自分らしさとしての性)
①性=Sex:生物学的な性。オス、メスについて
英語の履歴書の"Sex"だと性別を書く欄 "Male・Female" になっています。現在、オーストラリアだと、どちらでもないことで "X" と書けるようになっているそうです。
②Gender:ジェンダー(社会的性・文化的性)
社会・文化から生み出される性差のことを主に意味します。名前、服装、仕草、職業、昇給、最近だと大学の入学テスト問題など。生物学的な "Sex" とは違い、社会で生み出される性差。
ここでみなさんに考えてほしいこと!!
「力仕事が得意なのは、女性よりも男性である」は、これは生物学的な差異"Sex"か、社会的差異"Gender"なのか?
答え:両方
生物学的なこともあります。平均すると筋力は男性の方が上ですが、たくましい女性やか弱い男性が同じ場に居合わせることもあります。テーブル運ぶのは男の人の仕事だと社会は決めつけていませんか?
"他にも私だと「お茶を汲むので女の人きてください」と言われたら、腹が立ちます。まずはそういった日常にある些細と思われている会話にも腹を立ててほしいんです。少しおかしいと気がついてほしい。"
ジェンダーへの意識は、自分のもっていることへのおかしさに気がつくことから始まります。男性の中には、男性だからといって、力仕事をさせられることが苦痛な人もいます。
"教会でテーブル運ぶときに僕は「男の人、テーブル運ぶから手伝ってください」とは絶対に言わないです。「テーブル運ぶから力のある人、来てください」と言います。そうすると、力のある女性が手伝ってくれて、病み上がりの男性が「頑張って!」と座って外から応援するようになりました。
けど、ある方に 「『男の人、テーブル運ぶから来て』と言わないことにはとても賛同する。けど『力のある人、来て』と言うと、力のない人は『お前には用がない。邪魔だ』と言われているように感じるんです。」と言われたことがありました。僕はそんなつもりで言っていなかったので、びっくりしました。
テーブルくらいなら私も運べられるけど、周りの人から「いいよ、いいよ、あなたは座ってて」と言われたことがあるということ。配慮のつもりかもしれないけど、配慮じゃなくて、排除されているように感じるんです。それを聞いて私の言い方は完全に変わりました。
「テーブル運ぶから誰か来て」というようになりました。そうしたら、誰も手伝わなくなりました。完全に仕事が止まりました。"
仕事が止まってしまったことに困った平良さんでしたが、ある気づきがあったそうです。
"線引きをして役割分担を決めてしまうと、仕事が捗るけど、辛い思いをする人が時々いる。
線引きをしないと仕事が滞るけど、みんなが一緒になり楽な気持ちになる。さて、どっちがいいでしょうか?
私たちは効率主義に陥り、生産性を求めるようになりました。少しでも早く、たくさん仕事ができる方が良い、と刷り込まれているのです。そのために不要な線引きをして、排除する世界をつくっています。数年前に国会議員の方が「LGBTの人は生産性がないから、国がサポートするのは間違っている」という発言が問題になりました。国がサポートするのは、お国のために子どもを産む人だけであり、生産性のない人(子どもが産めない)に国がサポートする必要がないという主旨だったようです。その発言で、傷ついた人はLGBTの人だけではなく、何らかの理由で子どもをもうけることができない人も傷つきました。"
生産性を基準にしたときに、恐ろしいことが起きます。特に宗教者は、生産性を基準にすることがいかに危険なことか気がついてほしいんです。
ジェンダーを考える際に、生産性を最優先にしないために考えることは大事なことの一つです。
人にとやかく言われる筋合いがない「Sexuality(自分らしさとしての性)」
平良さんは、中学生になった頃からご自身が同性に惹かれることはとてもまずいことだと感じるようになったそうです。当時、色々本を読んでいましたが、どの本を見てもそのことを肯定してくれることはなかったそうです。物心ついた頃から同性が好きだった平良さん。
"将来を思い描いたときに僕が望んでいたのは、同性のパートナーと共に老後を過ごすことでした。たまに「平良さんは、いつから同性愛者なんですか?」と聞かれるんですが、その質問には難しくて答えられません。気がついたらそうでした、としか言えないです。そう聞いてくる人に「あなたいつから異性愛者なんですか?」と聞いても答えられないんですよ。私もそれと同じで、多くの人がいつのまにか、異性もしくは同性を意識するようになるのではないでしょうか。"
みんなと一緒に笑って、そして傷ついていくこころ
男同士がふざけてじゃれあっていると、先生が「おまえらホモか!気持ち悪い、離れろ!」と怒鳴りながら笑いをとるようなことがあり、それを見て生徒みんなが笑っていました。平良さんも笑っていたのですが、笑いながら傷ついてもいました。
高校生になると、「同性愛」という言葉に出会います。しかし、当時は本などでは「異常性欲」と書かれ、過去の出来事が現在の状況を作っている「原因論」として説明されていました。今では間違った理解だと言われます。しかし、当時はそれしか情報がないので、信じるしかなかったのです。
"原因論を信じると、私は「欠陥品だ」ということを受け入れることになります。私はこれからどう生きていきたいか、を知りたいだけなのに⋯⋯。同性のヌードなどを見て興奮したら、電気ショックを与える治療法も書かれていました。そんなの拷問のようで、恐怖を覚えました。自分が同性愛者だとバレたら拷問にあうと、心底怯えて、生涯このことは言わないで生きていこうと⋯⋯。
さらに言うと、高校がキリスト教の高校で、保守的なところで時代もあり、同性愛は罪と書かれていました。地獄いき、殺人より重く、神に逆らっていることだと。全ての人間に嫌われ、気持ち悪いと思われている。そして、神様からも嫌われている。そう思うと、生きていく場所がないと感じました。あの頃は、どうやって毎日、いのちを終わらせようかと考えていました。幸い僕は死ななかったですが。
断罪されていたのと同時に、自分を死なないように引き留めていたのもキリスト教だったのです。神はあなたに使命を与えている。それを追求して生きない。異性愛を貫きなさい。一生禁欲をつらぬきなさい⋯⋯。そんな感覚がありましたね。"
高校での経験もあり、どう生き抜いていこうか悩みに悩んだ平良さん。一生隠し通すと決めてはいましたが、ご自身にとって大事なことを隠し通すのは辛いこと。誰にも相談できないことで自身が壊れていくように感じたと言います。そんな時、カミングアウトをして親友にSOSをだしました。
"人生初めてのカミングアウトでした。「僕は男の人が好きなんだ」と恐怖に震え、汗と涙が止まらなくて、話すのに1時間かかりました。それでも、親友は「愛香は今までと同じ愛香だよ」と言ってくれて、すごく慰められました。"
初めてのカミングアウトが上手くいかない人も多くいます。「気持ち悪い」と言われたり、他の人にばらされる「アウティング」があることもあります。アウティングをされ、自死する人もいます。しかし、遺書には書きません。死んでも自分のことを隠したい人が沢山いるのです。
カミングアウトをされた時にどうしたらいいのでしょうか?平良さんは、カミングアウトをされて自分が抱えきれなくなっても勝手に周囲にそのことを話してはいけません。と言われます。どうしても話したければ、まずは本人に相談することが優先です。「自分一人では受け止めきれないから、〜〜さんに話していいですか?」と許可をもらうことが必ず必要です。それくらいアウティングは、本人にとって大きく大事なことなのです。
SOSのカミングアウトから、知ってほしいカミングアウトへ
平良さんが人生で初めてカミングアウトをして、気がついたことがあると言います。それは、親友に今までにたくさんの嘘をついていたことだったそうです。
「何か悩んでいることある?」には「ないよ」、「好きな人いるの?」には「いない」と自分を守るための嘘をついてきたと言うのです。カミングアウトをするとそういった会話にもちゃんと答えられるようになるのです。そうすると「もう嘘をつかなくてもいい」と気がつき、もっと他の親友にもカミングアウトをしたくなったそうです。そこで訪れたのが、2段階目のカミングアウトです。
1段階目のカミングアウトに隠れていた心は「SOS」。
2段階目のカミングアウトに隠れていた心は「本当の僕を知ってください。もう嘘をつきたくないです」。
そうすると、相手に求めることが変わってくるそうです。
"1段階目の時は「僕にとって愛香は今までと同じ愛香だよ」で嬉しかったけど、2段階目からは、受け止めてほしいと思うようになりました。「今までと同じ」と言われるとがっかりします。関係が新たに始まるのがカミングアウトの2段階目なんです。"
私の周りにLGBTはいない?!それは大間違い!
群馬県の短大に行かれていた平良さん。当時「府中青年の家裁判」という、同性愛者の団体が東京都の施設の利用を拒否されたのが問題になっていたそうです。この裁判の途中経過がゲイ雑誌に掲載されるようになり、同世代の人が本名で戦っている姿を目の当たりにしたと言います。それを見て「自分も何かしたい」と思い、第3のカミングアウトに繋がっていきます。
"短大の人権の講義で「同性愛者の人権もないがしろにされてるよね」と言えるようになりました。しかし、そこで他の学生から「同性愛の人権なんて考えたことなかった。だって見たことないし。平良さん見たことあるの?」と聞かれました。私は「あるよ(いつも鏡の前で見てる。いま話しているよ)」とその人に話したところ「私も見てみてみたい!」と言われました。その時に「他の人にとって同性愛者は見せ物なんだ⋯⋯」と感じ、「これじゃ差別はなくならない」と強く感じましたね。"
そこから、第3のカミングアウト「同性愛者はあなたの目の前にいます。気づいてください。差別しないでください」社会に対するカミングアウトに変わっていったそうです。
"LGBTの人は、自分のことを一生懸命隠しています。だから、「私の周りにLGBTの人はいないので、会ったことありません」と考えるのは大間違いです。LGBTの人はカミングアウトをしたくないわけじゃないんです。本当の理解者がいたら、少しでも理解者になってほしい、サポートしてほしいと思っています。だから、カミングアウトできる相手を探しています。だから、カミングアウトされたことがない人は、まだ選ばれてないってこと、信用されてないってことなんです。カミングアウトをしたい人は「この人は、受け止めてくれる素養があるな」と感じています。あなたがカミングアウトされる人にはどうするかを考えないといけないのです。悪いのはカミングアウトができない当事者ではないことはわかってほしいですね。"
同性愛と信仰
かつて、キリスト教と同性愛は相反するものだと捉えていた平良さん。しかし、キリスト教は同性愛を元々、ヘイトしていたわけではないことや、翻訳にも課題があったことを知り、キリスト教をもっと勉強していきたいと思ったそうです。
"僕の中でキリスト教と同性愛は相反するものではないと確信がでてきました。昔は、どちらかを捨てなきゃいけないと思っていたけど、どっちも捨てなくていいんだと思えるようになったんです。そして同時に、キリスト教に出会ったがために傷ついている人があまりに多いと気がつきました。そして、その人にエールを送らないといけないと感じましたね。それを伝えるために牧師になりました。"
当時、同性愛はダメだと思っている人が圧倒的に多い時代だったこともあり、平良さんの下には脅迫状もあったそうです。そんな中、牧師になるために東京に出て「動くゲイとレズビアンの会(現、NPOアンカー)」のメンバーになったそうです。そんな時にさらなる気づきが生まれます。
"メンバーに「平良さんは、どんな人がタイプなんですか?」聞かれたことがあります。その時、僕は「僕を好きになってくれる男性だったら誰でもいいですよ」と答えたら、「それは綺麗事です」と言われました。そこから「年上と年下どっち?」「太めと細めどっち?」とかを聞かれているうちに、僕にも好みがあると知りました。僕の中で、同性愛は選り好みをしてはいけないという思い込みがあり、自分にも偏りがあったんだと気がつきました。なんで、気がつかなったんだろうと思うと、孤独だったのだと思いました。
だから今、全国の同性愛者にエールを送りたいと思っています。あなたはひとりぼっちじゃない。孤立して寂しい思いをしている同性愛者にエールを送りたい。キリスト教に出会って傷ついた人にエールを送るのが、4段階目のカミングアウトになりました。"
<平良さんにおける、カミングアウトの段階>
1段階目は、SOS
2段階目は、本当の僕を知ってください。もう嘘をつきたくないんです
3段階目は同性愛者はあなたの目の前にいます。差別しないでください
4段階目は、当事者にエールを送る
100通りの生きづらさ
今回、平良さんからLGBTに関するたくさんの言葉を教えていただいた。最後に平良さんは、LGBTという4文字を使うことによる誤解が生まれることも教えてくださいました。
"LGBTの4文字をを使うと、4種類のセクシャリティと思われるけど、全然違います。100人いれば、100通りの性があり、100通りの生きづらさがある。LGBTは、生きづらさを押し付けられている、その代表として頭文字がとられているだけなんです。LでもGでもBでもTでもない、性的マイノリティがあるんです。100通りの生きづらさがあることをわかってほしいし、私たちが生きづらさを押し付けている側かもしれないと気づくことが大事なんです。"
平良さんは牧師さんでありながら、たくさんの仏教の僧侶から相談を受けているそうです。
"仏教の僧侶の方が、カミングアウトできるのは難しいかもしれないけど、わかってくれる仏教者が近くにいたらいいなと本当に思います。
親鸞聖人がお亡くなりになって750年の時に「親鸞さんへのお手紙」という企画があり、たくさんのお手紙があったようです。その中で佳作になって選ばれた手紙の一つが、浄土真宗の信者さんでトランスジェンダーの人の手紙でした。
「私は男性の体を持って生まれて、でも心は女性です。とても生きづらい。誰にも言えないんです。けどこの痛みを親鸞聖人さんだけがわかってくれる」。これを見て、とても感動したんです。だから、仏教の方にもいろんなことを知ってほしいと思っています。"
【編集後記】
「平良先生」ではなく、「平良さん」と呼んで講義を始めていきましょうと言われ、始まった講義。何気ないことでしたが、講義を受けていくと平良さんが言葉を丁寧に使われていたことに、少し日が経ってから身に染みてきたように感じました。それくらい配慮が行き届いた言葉が自然に、かつ丁寧に使われていたのです。
この講義ではこれから学ぶ「生きづらさ」の根っこに潜む、ちょっとした心のささくれや、気がついてもいなかったような感覚を平良さんの使う言葉、私の使っている言葉の点検をしていくような時間となりました。平良さんの生き方とジェンダーが抱える課題を社会的な大きな課題の一つではなく、一人ひとりの生活や言葉、態度から出現する課題を教えいただいたように思います。
次回の「思春期・若者支援コーディネーター養成研修会」は、2022年10月からスタートします。オンライン講座を中心にしながら、本願寺にて2回のスクーリングを実施します。現在申込み受付中ですので、ご関心のある方は下記より詳細をご覧ください。一緒に学び合える仲間と出会えることを楽しみにしています。
第4期 思春期・若者支援コーディネーター養成研修会 募集
【講師】平良愛香(たいらあいか)
1968年、沖縄県生まれ。2003年より、神奈川・相模原「日本キリスト教団三・一(さんいつ)教会」にて主任牧師を務める。現在、農村伝道神学校講師、日本聖書神学校特別講師、立教大学非常勤講師。1995年よりセクシュアル・マイノリティ・クリスチャンの集い「キリストの風」集会の代表のほか、カトリック・HIV/エイズデスク委員、「いのちの電話相談員全国研修会」講師を務めるなど、キリスト教以外でも幅広く活動中。セクシャリティ、ジェンダー、性差別の問題に取り組んでいる。また、出身地沖縄の基地問題に取り組んでいる。著書:『あなたが気づかないだけで神様もゲイもいつもあなたのそばにいる』『中高生からのライフ&セックス サバイバルガイド』
【執筆者】藤井一葉 (Fujii Kazuha)
浄土真宗本願寺派僧侶・所属、兵庫県宍粟市の山の麓にある無量山 願壽寺。若手僧侶グループ・ワカゾーで死をカジュアルに語る場「デスカフェ」を企画。 日本茶を淹れたり本を眺めているとほっとする。仏様のお話をさせていただくことも。
【研修情報】
思春期・若者支援コーディネーター養成研修会
主催:浄土真宗本願寺派 子ども・若者ご縁づくり推進室「思春期・若者支援部会」
お問い合わせ:goen@hongwanji.or.jp
SNS情報:子ども・若者ご縁づくりFacebook
