レポート
現代版寺子屋 スクール・ナーランダ vol.8 北海道
日 時: 2024年9月28日(土)・9月29日(日) 9:30~17:10
会 場: 本願寺小樽別院〔北海道小樽市若松1丁目4番17号〕
テ ー マ: 地球という船の上で ~多様な乗組員どうしの共生
講 師: 中川 裕(言語学者・アイヌ語研究者)
サヘル・ローズ(俳優・タレント)
寺本知正(浄土真宗本願寺派僧侶)
伊勢武史(森林生態学・環境学者)
鴻池朋子(アーティスト)
永田弘彰(浄土真宗本願寺派僧侶)
― 講義レポート ―
<1日目>
■「アイヌの伝統的な精神文化」 中川 裕先生
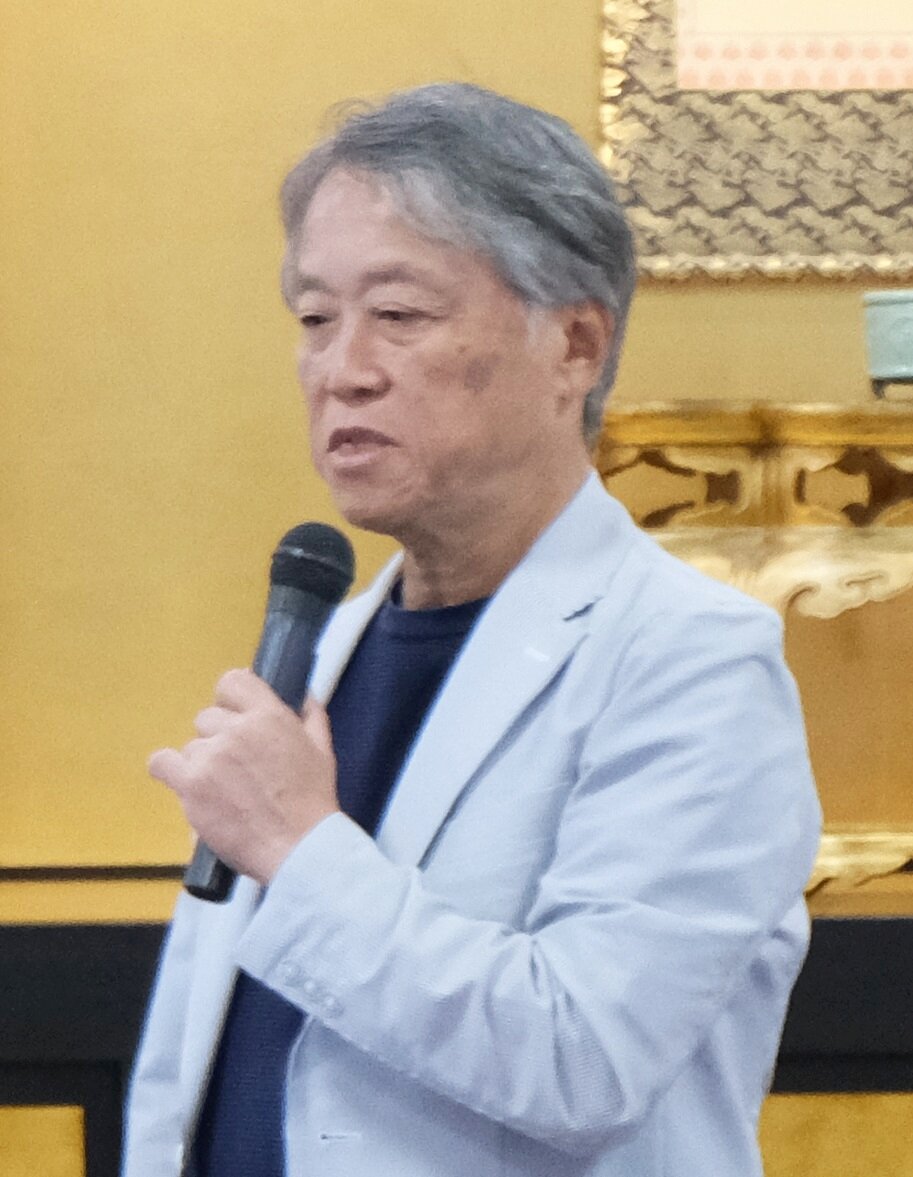 |
アイヌを知るにはカムイという言葉を知る必要があるとのことから、先ずはカムイについてお話いただきました。カムイとは神と訳されることが多いが、日本語でいう神とは違う。カムイは神でもなく、自然でもなく、人間を取り巻く、人間の生活に関わっているもの。家や舟や時計などもカムイであり、全てのものに肉体と魂があると考える。一番近い表現をするならば環境ではないだろうか。 人間はカムイからの贈り物で生活し、そのお礼として、カムイ自身が作れない酒や木弊などを送る。 また、アイヌの人たちは決して自然にある物だけを使うということではなく、新しいものを取り込み自分たちの生活が豊かになるよう生きてきた。現代社会においても、アイヌ的な生活をするということは、カムイとアイヌ―つまり環境と人間がお互いに感謝しながら共生していくことであり、これがアイヌの人たちが大切にしている思想であり精神文化であるとお話いただきました。 最後に全員で「スイ ウヌカㇻ アン ロ!」 また会いましょう! |
■「特別なことじゃない」 サヘル・ローズ先生
|
サヘル先生は幼少期にイランで体験した戦火の経験を語りながら、日々の生活の中で感じる戦争への思いをお話しされました。またその経験から「自分」の大切さを語り、自分を肯定して自分を愛していくことの重要性も説かれました。 サヘル先生が4歳の時にはすでに孤児院に入っておられ、7歳の時に現在の母親にあたる人物と出会い、その女性との養子縁組をキッカケに日本へと移り住むこととなりました。イランでは実現できなかった自由な信仰や教育の機会を得た一方で、出自や環境の違いから養子縁組先の親族や学校の同級生から偏見や差別を受けるといった辛い経験をされました。厳しい生活を送っていた先生ですが、ともすれば自分も銃を握っていたかもしれなかったことを考えると自身は幸運であったとも語られました。戦争経験者だからこそ、今起きている戦争というのは遠い出来事、全くの無関係ではないということを参加者に強く主張し、一人ひとりが意識していくことが大事であると締めくくりました。 |
 |
■「日常の中の宗教」 寺本 知正先生
 |
寺本知正先生は、宗教学の視点から、日常生活に潜む宗教的な要素について分かりやすく解説してくださいました。 たとえば、アクセサリーや化粧が実は宗教に起源を持つことを示し、日本神話に登場する天照大神が身につける緑色のネックレス「勾璁(まがたま)」を例に挙げられました。天照大神がこのネックレスを身につけることで超越的な力を得るように、アクセサリーや化粧には自分を超えた力を宿すという宗教的な意味が込められているのです。また、東南アジアの仏教において、得度の際に化粧をする儀式についても紹介されました。化粧によって、自らの身体を「力を持つ存在」へと作り変えるという考え方が説明されました。アクセサリーや化粧は、人を惹きつける力を与え、力強い存在へと変化させる宗教的な役割を果たしているのです。 寺本先生は日常に潜むこれらの宗教的な要素を意識することで、自分自身や周囲の世界とのつながりを再確認し、新たな発見や気づきを得られることを提案されました。 |
<2日目>
■「過去、現在、未来。人と自然の関りとその変化」 伊勢 武史先生
|
伊勢先生は森の植物の生態系を数式化し、地球温暖化による影響で100年先、200年先の森がどう変化していくのかシミュレーションする研究をされています。 原始時代は100万年続くが、人口は増えなかった。生きる事が厳しい時代は生存と繁殖にプラスになるよう特徴を持った人、つまり、自然を愛した人が生き残りやすかった。現代人は、お金や、手間、時間を費やしてまで森に遊びにいく。自然を愛するという人間の感情には生物学的な意味があるのではないかと考えているそうです。 また、進化心理学は今を生きる私たちに必要だそうです。例えば夜中にお菓子を食べることは体に悪い事だとわかっているが、正論を押し付けても人は動かない。人を動かすときには快く感じさせることが重要で、実行できた人が生き残ってきたから今の人間がいると考えられています。 人間は将来を考える事ができる。未来が良くなるために、エコ活動を楽しく感じさせる事も大切であるとお話しくださいました。 |
 |
■「自分の好きなことを否定しない」 鴻池 朋子先生
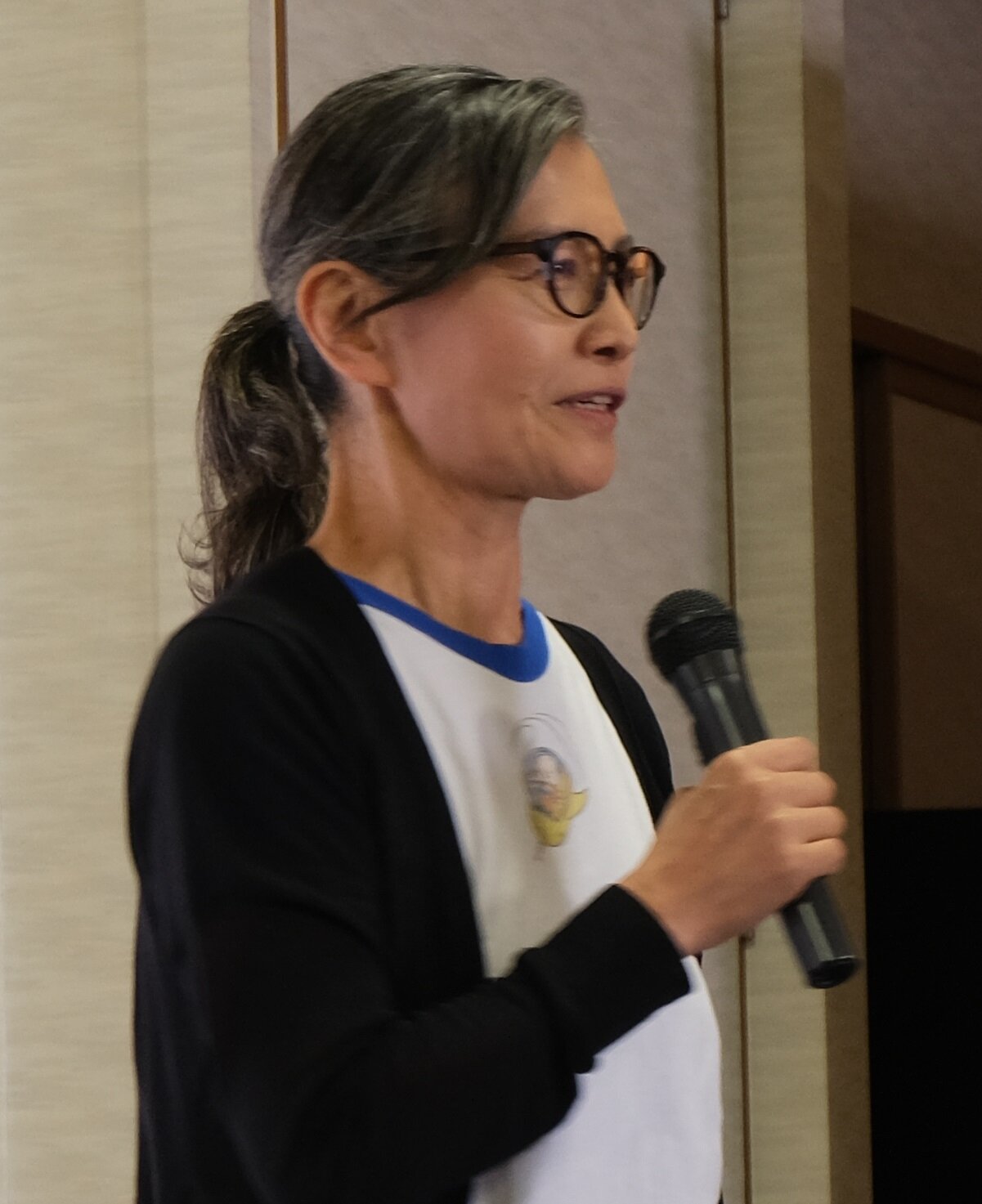 |
鴻池さんの講義は、枠にとらわれた情報ではなく、自分自身が感じることを重視されていました。また、その中でアートが、美術教育の中ではたせる可能性も語られました。学校の美術授業が構造的で言葉に偏りがちな点を指摘し、実際にふれる体験やそこで学生たち一人ひとりが抱く感覚の重要性を話されました。そこに、美術の決まった授業の枠にとらわれない生き方の「抜け道」としてのありよう、生きる力を見つける場にする意義を説きました。 生きづらさを感じて学校に入っている人がもしいるなら、アートという抜け道が授業という「みんなといる」中で「自分だけの場所」をつくる契機となること。保健室でもトイレでもない、たった一人の場所だけではなく、授業という外、他の学生や先生とつながりのある空間で自分の居場所、抜け道を見つけていける可能性についてもふれました。最後に「自分の好きなことや、小さな小さな自分の気持ちも否定せず、呼吸する工夫を大切に」とのメッセージを送り、一人ひとりのもつ感性に想いをよせられていました。 |
■「物事の背景のストーリー的見方」 永田 弘彰先生
|
永田先生は、まず全てのものは繋がり合って存在しているという仏教の「縁起」という考え方について、ご自身の体験を通して、親しみやすく、また漫談のように面白く、かつ分かりやすくお話くださいました。 そして、物事を見るときは、その実体だけを見るのではなく、それに至った背景にあるストーリーを見ることが大切であり、それにより人生が大きき変わり、豊かなものとなるとご提案くださいました。 例えば、先生は檀家さんから、京都のお土産で「八つ橋」をいただいた時、とても嬉しかったそうです。「八ツ橋」はいまではオンラインでも購入できます。しかし、そのお土産をいただい時、その檀家さんが自分の全く知らない時に、遠く離れた場所で、自分のことを考えてくれて、喜ぶ顔を思い浮かべてくれたから、この「八つ橋」が手元に届いたということに気づかれたそうです。お土産の「八つ橋」の背景にあるストーリーを見ることで、同じ「八つ橋」でも、見え方が大きく違ってくる、そのストーリー見ることで人生がより豊かなものとなるとお教えてくださいました。 |
 |
